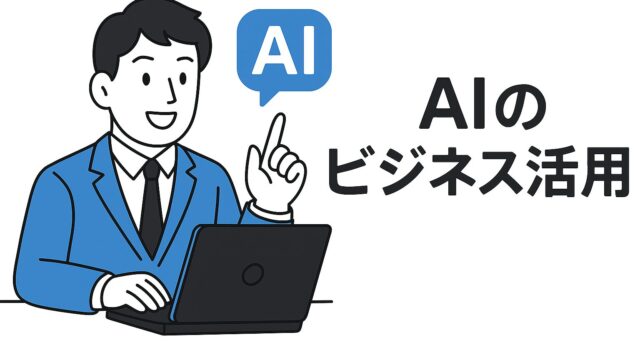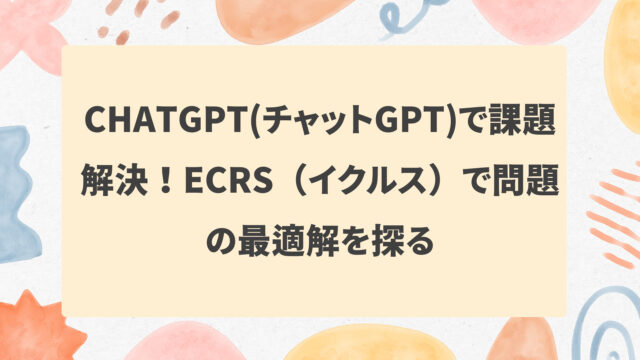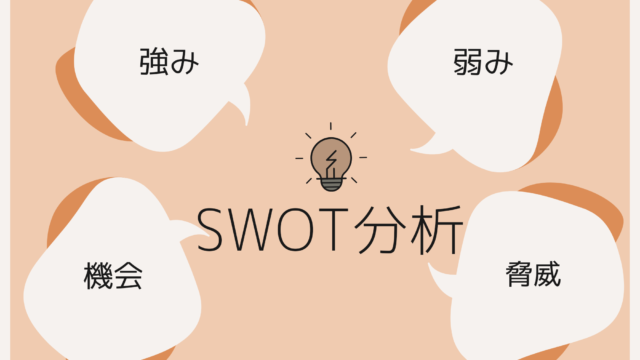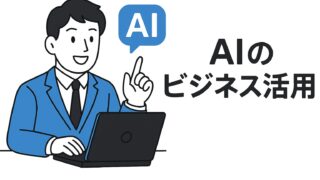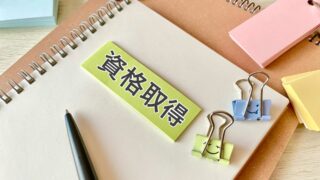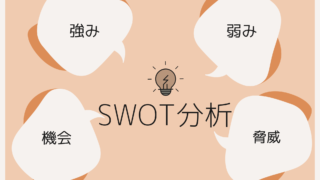【生成AIで作る契約書の完全ガイド】用途別の手順・注意点を徹底解説(プロンプト付き)ChatGPT・Geminiで作成業務が3分の1に
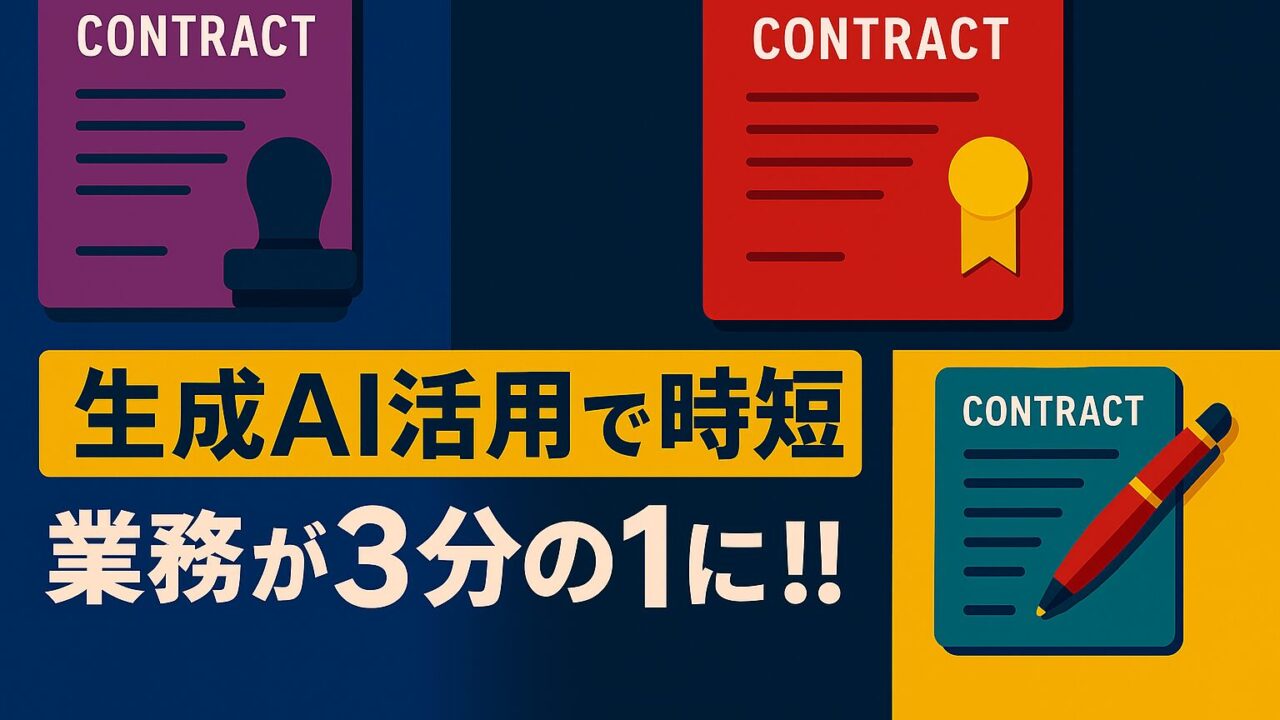
「契約書作成、もっと効率化できないか…」そんな悩みを抱える法務担当者やビジネスパーソンへ。ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIは、契約書ドラフティング業務を劇的に変え、作業時間をリアルに3分の1に短縮する可能性を秘めています。
しかし、AIの活用には適切な手順と注意点の理解が不可欠です。
この記事では、生成AIで各種契約書を作成するため、 秘密保持契約書 (NDA)から業務委託契約書、売買契約書まで、用途別の具体的な手順をステップバイステップで解説。
さらに、AI利用時の見落としがちな法的注意点やリスク回避策、そしてコピペしてすぐに使える実践的なプロンプト例まで、網羅的にご紹介します。
本記事を読めば、あなたもAIを契約業務の強力な味方にできるはずです。
AI利用の心構え
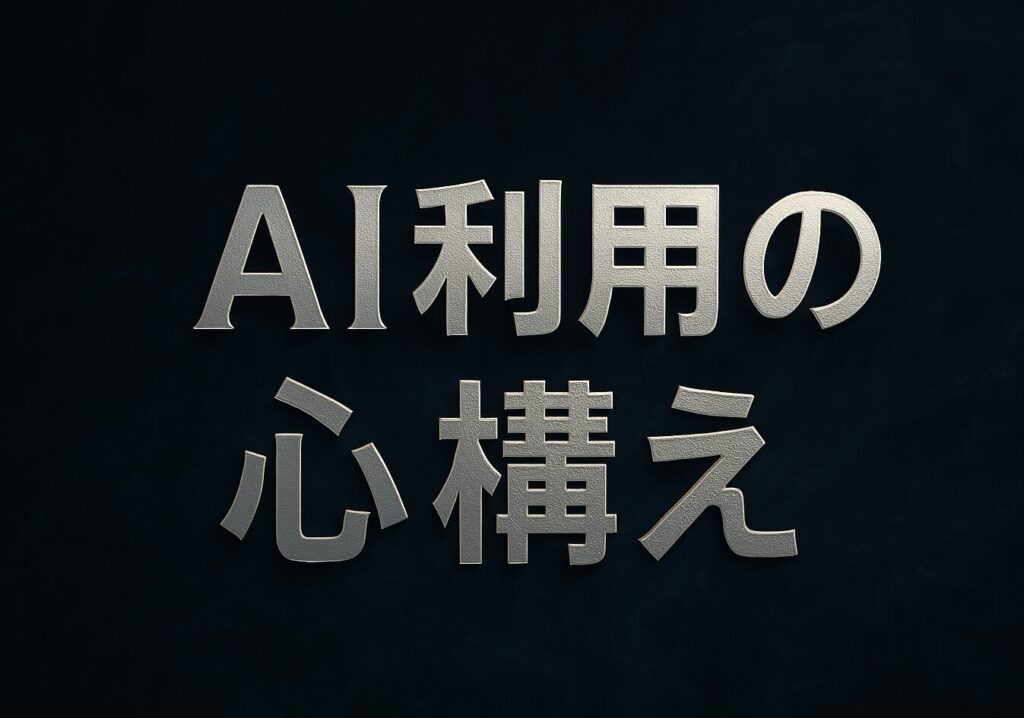
- AIはあくまで「下書き作成支援ツール」
AIは法律の専門家ではありません。生成された文章は、法的な有効性や抜け漏れのなさ、個別の状況への適合性が保証されるものではありません。最終的な判断と責任は必ず人間が負う必要があります。 - 「法律専門家によるレビュー」は必須工程
AIが生成した契約書案は、必ず弁護士などの法律専門家による確認・修正を受けてください。 なぜなら、AIは最新の法改正や関連判例、特定の業界における慣行、あるいは契約に至るまでの当事者間の細かな交渉経緯などを完全に反映できない可能性があるためです。専門家のチェックを経ずに使用した場合、予期せぬトラブルや法的なリスクを負う可能性があります。 - プロンプト(指示)の質が結果を左右する
AIにどのような契約書を作ってほしいのか、できるだけ具体的かつ正確な情報を伝えることが重要です。曖昧な指示では、一般的で役に立たない、あるいは意図と異なる内容の草案しか生成されません。契約の目的、当事者、主要な条件(期間、金額、対象物、義務内容など)を明確にしてからプロンプトを作成しましょう。 - 機密情報の取り扱いには細心の注意を
利用するAIサービスによっては、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があります。契約に関する情報、特に当事者名や取引内容などの機密性の高い情報を入力する際には、そのAIサービスのプライバシーポリシーや利用規約を事前に確認し、リスクを理解した上で利用してください。

AIによる契約書作成の一般的な流れ

- 目的と主要条件の明確化
まず、「何のための契約か」「誰と誰が結ぶのか」「期間はいつまでか」「金額はいくらか」「何を対象とするか」「お互いに何をすべきか(義務)」といった契約の骨子を整理します。ここが曖昧だと、後の工程で手戻りが多くなります。 - プロンプトの作成
上記で整理した情報を基に、AIへの具体的な「お願い(指示)」を作成します。後述のプロンプト例を参考に、必要な情報を盛り込みます。 - AIによる草案生成
作成したプロンプトをAIツールに入力し、契約書の草案を出力させます。 - 内容の精査と修正
AIが生成した草案を注意深く読み込みます。「契約の目的に合っているか?」「必要な条項は全て含まれているか?」「不足している点はないか?」「逆に、自社に不利な、あるいは意図しない条項が入っていないか?」などを確認します。必要であれば、AIに追加指示を出して修正させたり、自身で直接修正したりします。(※この段階ではまだ「案」です) - 専門家によるレビューと最終化
修正した契約書案を弁護士などの法律専門家に見てもらい、法的な観点から問題がないか、リスクが潜んでいないかなどをチェックしてもらいます。専門家からの指摘事項を反映し、最終的な契約書を完成させます。この工程を省略してはいけません。
【用途別】手順・注意点・プロンプト例

1. 秘密保持契約書 (NDA)
目的
自社が持つ「秘密にしておきたい情報(技術、ノウハウ、顧客リストなど)」を取引先などに開示する必要がある場合に、その情報を「目的外で使われたり」「勝手に他人に漏らされたり」するのを防ぐための契約です。情報開示の「前」に締結するのが基本です。
手順
- 当事者(情報を開示する側「開示者」、情報を受け取る側「受領者」)を明確にします。
- 何を「秘密情報」とするか定義します。 ここが最も重要です。口頭で伝えた情報も含むのか、特定のマークを付けたものに限るのか、例外(既に公開されている情報など)はあるか、などを具体的に定めます。曖昧だと保護範囲が不明確になります。
- 何のために情報を開示するのか(例:「〇〇の共同開発検討のため」)を特定します。これにより、受領者が情報を利用できる範囲が限定されます(=目的外利用の禁止)。
- 受領者の主な義務(目的外利用の禁止、第三者への原則開示禁止、情報を適切に管理する義務など)を定めます。
- いつまで秘密を守る義務を負うか(秘密保持期間)を定めます(例:契約終了後3年間など)。情報の性質によって適切な期間は異なります。永久に、というのは現実的でない場合が多いです。
- 契約終了時や開示者の要求があった場合に、受け取った情報をどうするか(返却するのか、破棄するのか、破棄したことを証明するのか)を定めます。
- どの国の法律を基準にするか(準拠法)、万が一紛争になった場合にどの裁判所で争うか(合意管轄)を定めます。これにより、紛争時の手続きが明確になります。
- 上記を盛り込んだプロンプトを作成し、AIに草案を生成させます。
- 生成された草案を確認し、特に「秘密情報の定義」「開示目的」「例外規定」「秘密保持期間」が自社の意図と合っているか、厳しくチェックし修正します。
- 専門家レビューを受け、最終版とします。
注意すべき点
- 「秘密情報」の定義は具体的かつ明確に。保護したい情報がきちんとカバーされているか、逆に、保護する必要のない情報まで含まれていないか確認が必要です。
- 例外的に開示が許されるケース(法令に基づく開示命令など)も明記しておくのが一般的です。
プロンプト例
●[甲](開示者)と[乙](受領者)の間で締結する秘密保持契約書の草案を作成してください。
●契約の目的は『[具体的な取引やプロジェクト名、検討目的など]に関する情報交換』です。秘密情報の定義としては、甲から乙へ開示され、秘密である旨が明示された技術情報、営業情報、顧客情報、その他一切の情報とし、公知の情報や乙が独自に開発した情報などは除外してください。
●受領者の主な義務として、秘密情報の目的外使用の禁止、書面による事前承諾なき第三者への開示禁止、適切な情報管理体制の構築を盛り込んでください。
●秘密保持期間は本契約締結日から契約終了後[○○]年間とし、契約終了時または甲の要求時には、情報を速やかに返還または破棄する義務、そして義務違反があった場合の損害賠償責任についても定めてください。
●準拠法は日本法、合意管轄は[○○]地方裁判所(専属的合意管轄)としてください。」
2. 業務委託契約書
目的
自社の業務の一部(例:システム開発、デザイン制作、経理代行、コンサルティングなど)を、外部の事業者(法人または個人)に依頼(委託)する際に、その業務内容、対価(報酬)、成果物の権利、責任の範囲などを明確にするための契約です。
手順
- 当事者(業務を依頼する側「委託者」、業務を引き受ける側「受託者」)を明確にします。
- 委託する業務の内容、範囲、要求される水準(仕様)を、可能な限り具体的に特定します。 ここが曖昧だと「言った・言わない」のトラブルの元です。「別途『仕様書』で定める」場合は、その仕様書が契約の一部であることを明記します。
- 業務の結果として納品されるもの(成果物。プログラム、報告書、デザインデータなど)があれば、その内容、納品方法、委託者がOKを出すための検査(検収)方法や期間を定めます。検収合格が報酬支払いの条件となることが多いです。
- 契約期間(いつからいつまでか)または業務完了までの期間を定めます。
- 報酬(委託料)の金額、計算方法(月額固定、成果物ごと、時間単価など)、支払条件(例:検収合格後、月末締め翌月末払いなど)を明確にします。
- 成果物に関する知的財産権(著作権、特許権など)がどちらに帰属するかを明確に定めます。 特にソフトウェア開発やデザイン制作などでは極めて重要です。委託者に帰属させるのか、受託者に留保するのか、共有するのかなどを決めます。(※「著作者人格権」の不行使についても定めることがあります)
- 受託者がさらに別の事業者に業務を委託(再委託)することを認めるか、認めるとした場合の条件(委託者の事前承諾など)を定めます。
- 業務上知り得た相手方の秘密情報の取り扱い(秘密保持義務)について定めます(NDAを別途締結する場合もあります)。
- どのような場合に契約を途中で終了(解除)できるかを定めます(重大な契約違反があった場合など)。
- 契約違反があった場合の損害賠償責任について定めます(責任の上限額を設けることもあります)。
- 準拠法と合意管轄を定めます。
- 上記を盛り込んだプロンプトを作成し、AIに草案を生成させます。
- 生成された草案を確認し、「業務内容の特定」「成果物と検収」「報酬」「知的財産権の帰属」「責任範囲(契約不適合責任含む)」が明確かつ意図通りかを確認・修正します。
- 専門家レビューを受け、最終版とします。
注意すべき点
- 業務内容は具体的に。受託者の責任範囲(どこまで保証してくれるのか。例:納品後〇ヶ月間の不具合修正は無償対応など)も確認が必要です。
- 知的財産権の帰属は、将来の利用やビジネス展開に大きく影響するため、慎重に決定・明記する必要があります。
プロンプト例
●[委託者名](甲)が[受託者名](乙)に業務を委託するための業務委託契約書の草案を作成してください。
●委託する業務内容は『[具体的な業務内容。例:甲のウェブサイトにおける特定の機能の開発]』とし、詳細は別途定める仕様書に従うものとします。
●成果物として『[仕様書に定めるプログラム]』を期待しており、納期は『[○○〇〇年○○月○○日]』です。成果物納入後、甲は『[〇]営業日』以内に検査し、合否を乙に通知します。
●委託料は『[総額〇〇円(消費税別)]』とし、支払条件は『[検収合格後、当月末締め翌月末までに乙指定の銀行口座に振り込む]』とします。
●本業務により生じた成果物に関する知的財産権は、『[委託料の完済をもって甲に帰属する]』としてください。
●再委託は『[甲の書面による事前承諾を得た場合に限り可能]』とし、相互に秘密保持義務を負う条項も入れてください。
●契約期間、重大な違反があった場合の解除条件、債務不履行時の損害賠償責任(損害賠償の上限を設ける場合はその額も)、準拠法(日本法)、合意管轄([○○裁判所]、専属的合意管轄)に関する条項も含めてください。
3. 簡易的な賃貸借契約書
目的
不動産(土地、建物全体、部屋、事務所スペースの一部など)を貸し借りする際の条件(賃料、期間、使用目的など)を定める契約です。
手順
- 当事者(貸す側「貸主」、借りる側「借主」)を明確にします。
- 賃貸借の対象となる物件を正確に特定します(所在地、建物名、階数、部屋番号、対象面積など)。図面を添付するのが望ましいです。
- 物件を何のために使うのか(使用目的。「事務所として利用」など)を定めます。目的外の利用は通常禁止されます。
- 契約期間(いつからいつまで借りるか)を定めます。
- 賃料(家賃)、共益費(管理費など)の金額、支払方法(振込など)、支払期日(毎月〇日までに翌月分を支払う)を定めます。
- 敷金(※家賃滞納や原状回復費用の担保として預けるお金。通常、契約終了時に精算して返還される)や礼金(※貸主への謝礼として支払われ、返還されないお金)の有無、金額、敷金の返還条件を定めます。
- 禁止される行為(貸主の許可なく増改築すること、ペットを飼うこと、又貸し(転貸)すること、危険物を持ち込むことなど)を具体的に列挙します。
- 物件の修繕が必要になった場合の費用負担(どちらがどの範囲の修繕を行うか)を定めます(電球交換など小規模修繕は借主負担、雨漏りなど大規模修繕は貸主負担、など)。
- 契約の更新手続きや、契約を途中で解除する場合の条件(〇ヶ月前に予告するなど)を定めます。
- 契約終了時に物件を明け渡す際のルール、特に「原状回復義務」(※借りた時の状態に戻す義務。ただし、普通に使っていて生じる損耗=通常損耗は含まないのが一般的)の範囲について定めます。
- 準拠法と合意管轄を定めます。
- 上記を盛り込んだプロンプトを作成し、AIに草案を生成させます。
- 生成された草案を確認し、特に「目的物の特定」「賃料・支払条件」「禁止事項」「修繕義務」「原状回復義務の範囲」が明確か、意図通りかを確認・修正します。
- 【最重要】必ず専門家(宅地建物取引士、弁護士など)に相談・レビューを依頼、または作成を依頼してください。
注意すべき点
- 不動産賃貸借は、借地借家法などの特別な法律(強行法規=当事者の合意よりも優先される法律)によって、貸主・借主双方の権利義務が細かく定められています。 AIが生成したものがこれらの法律に適合している保証は全くありません。安易な利用は極めて危険です。居住用物件や事業用物件全体を借りる場合は、専門家の関与が不可欠です。
- 原状回復の範囲は、トラブルが非常に多い点です。どこまでが借主の負担で、どこからが通常損耗として貸主負担になるのか、国土交通省のガイドラインなども参考に、可能な限り具体的に合意しておくことが望ましいです。
プロンプト例
●[貸主名](甲)と[借主名](乙)の間で締結する不動産に関する賃貸借契約書の草案を作成してください。これはあくまで簡易的な草案であり、必ず専門家によるレビューを受けることを前提とします。
●目的物は『[物件所在地、建物名、〇階]』(詳細は別添図面参照)とし、使用目的は『[乙の具体的な事業内容]のための事務所』です。
●契約期間は『[○○○○年○○月○○日]から[○○○○年○○月○○日]までの[〇]年間』、賃料は月額『[〇〇]円(消費税別)』、共益費は月額『[〇〇]円(消費税別)』とし、毎月末日までに翌月分を甲指定口座へ振り込むものとします。
●敷金として『[〇〇]円』を預託し、契約終了後、原状回復費用等を控除し、明け渡し後『〇ヶ月以内』に乙に返還するものとします。
●禁止事項として、甲の書面による事前承諾なき構造変更、増改築、転貸、危険物の持ち込み、騒音・振動・悪臭の発生を挙げてください。
●修繕義務は、通常の使用に伴う小規模修繕は乙負担、建物の基本構造部分は甲負担とします。
●賃料支払遅延(〇ヶ月以上)や禁止事項違反があった場合の契約解除条項、契約終了時に乙が自己の費用で原状に回復して明け渡す義務(通常損耗を除く)に関する条項、準拠法(日本法)、合意管轄([例:横浜地方裁判所]、専属的合意管轄)も含めてください。
4. 売買契約書
目的
特定の「物品」(商品、製品、機械など、形のある動産)を、売り手(売主)が買い手(買主)に渡し、買い手がその代金を支払うことを約束する、最も基本的な取引契約の一つです。
手順
- 当事者(売主、買主)を明確にします。
- 売買の対象となる物品(目的物)を、品名、型番、数量、品質、仕様などで、誰が見ても特定できるように具体的に記載します。 ここが曖昧だと、後で違うものが納品された等のトラブルになります。
- 売買代金の総額、単価、消費税の扱い、支払方法(振込、手形など)、支払時期(納品後〇日以内、検収合格後〇日以内など)を定めます。
- 物品をいつ、どこで、どのように引き渡すか(引渡し)を定めます。輸送費をどちらが負担するかも明確にします。
- 物品の所有権がいつ売主から買主に移るか(所有権移転時期)を定めます。 一般的には「引渡し時」または「代金完済時」とすることが多いです。代金回収リスクを考える売主にとっては「代金完済時」が有利ですが、買主は早く所有権を得たいと考えます。
- 危険負担について定めます。これは、引渡し前に、売主・買主いずれのせいでもなく物品が壊れたり無くなったりした場合(天災など)、その損失リスクをどちらが負うかという問題です。 民法では引渡し時に危険負担が移転するのが原則ですが、契約で別途定めることも可能です(買主が指定した運送業者に引き渡した時点で移転するなど)。
- 買主が、引き渡された物品が契約内容(品質、数量、仕様など)に合っているかを確認する検査(検収)の方法、期間、合格基準を定めます。
- 引き渡された物品に、種類、品質、数量に関して契約内容と異なる点(契約不適合)があった場合の売主の責任(契約不適合責任)について定めます。 買主は、修補(修理)、代替物の引渡し、代金減額、損害賠償、契約解除などを請求できます。どの責任を、いつまで(引渡し後〇ヶ月以内)負うのかを具体的に定めます。(※これは以前の「瑕疵担保責任」に代わる考え方です)
- どのような場合に契約を解除できるかを定めます(代金不払い、引渡し遅延など)。
- 準拠法と合意管轄を定めます。
- 上記を盛り込んだプロンプトを作成し、AIに草案を生成させます。
- 生成された草案を確認し、「目的物の特定」「引渡し条件」「所有権移転時期」「危険負担」「契約不適合責任の内容と期間」が自社の意図と合っているか、法的に問題ない範囲か(責任期間など)を確認・修正します。
- 専門家レビューを受け、最終版とします。
注意すべき点
- 契約不適合責任の期間や内容は、民法の規定よりも買主に不利にならない範囲で、当事者間の合意で定めることが可能です。自社のリスク許容度に応じて検討が必要です。
- 国際取引の場合は、インコタームズ(貿易条件)なども考慮に入れる必要があります。
プロンプト例
●[売主名](甲)と[買主名](乙)の間で締結する物品売買契約書の草案を作成してください。
●目的物は『[商品名、型番、仕様など]』で、数量は『[〇個]』、品質は『[甲乙別途合意する品質基準/甲の標準仕様に準拠など]』とします。
●売買代金は総額『[〇〇]円(消費税別)』で、支払条件は『[乙による検収合格後、〇日以内に甲指定の銀行口座に振り込む]』としてください。
●引渡しは『[○○○○年○○月○○日]』に『[乙の指定する場所/甲の工場渡しなど]』で行い、引渡しをもって危険負担は乙に移転するものとします。
●所有権は『[売買代金全額の支払完了時]』に乙に移転すると定めてください。乙は引渡し後『[〇]営業日』以内に検査を行い、合否を甲に通知するものとします。
●契約不適合責任については、引渡し後『[〇ヶ月/〇年間]』以内に発見された契約不適合に関し、甲が『[修補、代替物引渡し、代金減額などから選択、または具体的対応]』の責任を負うものとし、ただし乙の責に帰すべき事由による場合は免責される条項を入れてください。
●代金不払いなど重大な違反があった場合の契約解除条項、準拠法(日本法)、合意管轄([○○地方裁判所]、専属的合意管轄)も含めてください。
5. コンサルティング契約書
目的
ある分野の専門家(コンサルタント)が、依頼主(クライアント)に対して、専門的な知識や経験に基づく助言、指導、調査、分析などのサービス(コンサルティング業務)を提供する際の条件を定める契約です。形のある「モノ」ではなく、「役務(サービス)」の提供が中心となります。
手順
- 当事者(サービスを受ける側「クライアント」、提供する側「コンサルタント」)を明確にします。
- どのようなコンサルティング業務を行うのか、その範囲、内容、目的をできるだけ具体的に定義します。 「〇〇に関する助言」だけだと曖昧すぎるため、「〇〇に関する市場調査と分析レポート作成」「〇〇システムの導入支援と操作指導」のように特定します。スコープ(範囲)外の業務は別途協議とすることも明記します。
- 業務の成果として提出されるもの(報告書、分析資料、提案書など)があれば、その内容、提出方法、提出時期を定めます。「月次報告」など定期的な報告義務を定めることもあります。
- 契約期間(いつからいつまでか)または業務実施期間を定めます。プロジェクト単位か、顧問契約のような継続的なものかで異なります。
- 報酬の金額、算定方法(月額固定の顧問料、時間単価×作業時間(タイムチャージ)、プロジェクト全体の固定料金(プロジェクトフィー)、成果に応じた成功報酬など)、支払条件を明確にします。
- 知的財産権の取扱いを定めます。 コンサルタントが作成した報告書などの著作権は誰に帰属するのか? クライアントはその成果物をどのように利用できるのか? コンサルタントが元々持っているノウハウや手法の権利はどうなるのか?などを明確にします。
- 業務遂行上、相互に知り得た相手方の秘密情報を守る義務(秘密保持義務)について定めます。
- コンサルタントの責任範囲を定めることが一般的です。 コンサルティングは助言であり、必ずしも特定の結果を保証するものではないため、「善良なる管理者の注意をもって業務を遂行する」義務(善管注意義務)にとどめたり、万が一損害が発生した場合の賠償額に上限(受領済み報酬額まで)を設けたりすることが多いです。クライアント側はその内容が妥当か検討が必要です。
- 契約を解除できる条件を定めます。
- 準拠法と合意管轄を定めます。
- 上記を盛り込んだプロンプトを作成し、AIに草案を生成させます。
- 生成された草案を確認し、「業務範囲の明確性」「成果物の定義」「報酬体系」「知的財産権の帰属と利用範囲」「責任制限条項」が意図通りか、自社にとって受け入れ可能かを確認・修正します。
- 専門家レビューを受け、最終版とします。
注意すべき点
- 業務範囲の明確化は、後の「スコープクリープ」(当初予定していなかった業務まで要求されること)を防ぐために非常に重要です。
- 責任制限条項は、コンサルタントにとってはリスク管理上重要ですが、クライアントにとっては不利になる可能性があるため、内容をよく理解し、交渉が必要な場合もあります。
プロンプト例
●[クライアント名](甲)と[コンサルタント名](乙)の間で締結するコンサルティング契約書の草案を作成してください。
●コンサルティング業務内容は『甲の[対象分野、例:新規事業開発]に関する助言、指導、調査分析』とし、具体的なテーマや範囲は別途協議の上、書面で合意するものとします。
●成果物として『[月次報告書及び最終報告書]』を提出するものとし、契約期間は『[○○○○年○○月○○日]から[○○○○年○○月○○日]まで』とします。
●報酬は『[月額固定〇〇円(消費税別)]』とし、支払条件は『[毎月末締め、翌月末までに乙指定の銀行口座に振り込む]』とします。
●本契約に基づき乙が作成し甲に提供した成果物の著作権は『[報酬の完済をもって甲に移転する]』ものとし、甲はその成果物を業務目的の範囲内で自由に使用できるものとします。
●相互の秘密保持義務に関する条項も入れてください。
●責任については、乙は善良なる管理者の注意をもって業務を遂行するが特定の結果達成を保証しないこと、乙の責に帰すべき事由による損害賠償額は『[既に受領した報酬額]』を上限とすることを明記してください。
●重大な違反があった場合の契約解除条項、準拠法(日本法)、合意管轄([○○地方裁判所]、専属的合意管轄)も含めてください。
6. 金銭消費貸借契約書
目的
お金を貸し借りする際に、その金額、利息、返済方法、返済期限などの基本的な条件を定める契約です。個人間、事業者間、金融機関と事業者・個人など、様々な場面で用いられます。
手順と補足
- 当事者(お金を貸す側「貸主」、借りる側「借主」)を明確にします。
- 貸し付ける金額(元本)を正確に記載します。
- 利息を定める場合は、その利率(年利%)と計算方法(例:年365日の日割計算)を定めます。 ここで最も注意すべきは、利息制限法で定められた上限利率(元本額に応じて年15%~20%)を超えてはいけないということです。上限を超える利息部分は無効となります。
- どのように返済していくか(返済方法)を具体的に定めます。一括返済か、分割返済か。分割の場合は、毎回の返済額、返済日、最終的な返済期日を明確にします。
- 返済が遅れた場合のペナルティ(遅延損害金)の利率を定めます。 これも利息制限法等で上限(上限利率の1.46倍まで、ただし年20%が上限となる場合が多い)が定められています。上限を超える部分は無効です。
- 借主が返済した金銭を、費用→遅延損害金→利息→元本のどの順序で充当するか(弁済の充当順序)を定めます。
- 期限の利益喪失条項を定めます。 これは、借主が特定の約束違反(分割返済を〇回以上怠った、破産したなど)をした場合に、本来なら分割で返済できたはずの「期限の利益」を失い、貸主の請求によって残額全てを一括で返済しなければならなくなる、という貸主保護のための重要な条項です。どのような場合に期限の利益を失うかを具体的に列挙します。
- 担保(借主が返済できなくなった場合に備えて、不動産や動産などを確保しておくこと)や保証人(借主が返済できない場合に代わりに返済義務を負う人)を設定する場合は、その内容を契約書に明記します。(※別途、抵当権設定契約や保証契約などの手続きが必要となる場合が多いです)
- 準拠法と合意管轄を定めます。
- 上記を盛り込んだプロンプトを作成し、AIに草案を生成させます。
- 生成された草案を確認し、特に「金額」「利率(上限遵守!)」「返済計画」「遅延損害金利率(上限遵守!)」「期限の利益喪失事由」が正確か、法的に問題ないかを厳しく確認・修正します。
- 必ず専門家(弁護士、司法書士など)に相談・レビューを依頼してください。
注意すべき点
- 金銭消費貸借契約は、利息制限法、出資法などの法律で厳しく規制されており、違反すると民事上無効になるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性すらあります。 AIはこれらの複雑な法規制を完全に理解・遵守して生成するとは限りません。事業性の貸付や高額な貸付、担保・保証が絡む場合は、絶対に自己判断せず、専門家の助言・関与が不可欠です。
- AIによるドラフト作成は、あくまで契約条件の整理や、専門家への相談資料のたたき台作成補助としてのみ利用すべき分野です。
プロンプト例
●【警告:これは金銭消費貸借契約の草案作成依頼です。利息制限法等の法令遵守が絶対条件です。】 以上の点を理解した上で、以下の条件に基づき、[貸主名](甲)と[借主名](乙)の間で締結する金銭消費貸借契約書の草案を作成してください。
●貸付実行日は『[○○○○年○○月〇〇日]』、貸付金額(元本)は『金[〇〇]円』とします。利息は『年[〇〇]%(年365日の日割計算)』(※利息制限法の上限内であることを要確認)とし、返済方法は『[○○○○年○○月]から[○○○○年○○月]まで、毎月[〇]日限り、金[〇〇]円(元利均等/元金均等など)を甲指定銀行口座へ振込』、最終返済期日は『[○○○○年○○月○○日]』とします。
●遅延損害金は『年[〇〇]%(年365日の日割計算)』(※法定上限内であることを要確認)とし、弁済の充当順序は費用・遅延損害金・利息・元本の順と定めてください。
●期限の利益喪失条項として、乙が分割金の支払いを『[〇]回以上』怠ったとき、乙について破産手続開始等の申立てがあったとき、その他本契約条項に違反したときは、甲からの通知催告なくして当然に期限の利益を喪失し、乙が残債務全額を直ちに弁済する義務を負う旨を規定してください。
●担保・保証人として『[設定する場合は具体的に記載。例:乙は本債務担保のため乙所有不動産に抵当権を設定する/丙は乙の本債務を連帯保証する]』という条項も(もしあれば)含めてください。
●準拠法は日本法、合意管轄は『[○○地方裁判所](専属的合意管轄)』としてください。
7. 業務提携契約書
目的
複数の事業者(会社や個人事業主)が、それぞれが持つ強み(技術、ノウハウ、販売網、ブランド力、顧客基盤など)を出し合い、協力して新しい事業やプロジェクトを進める(=業務提携)際の、基本的なルール(目的、役割分担、費用負担、収益分配、知的財産の扱いなど)を定める契約です。新しい会社(合弁会社など)を設立するのではなく、各々が独立性を保ったまま協力する場合に用いられます。
手順
- 提携する当事者(会社名など)を明確にします。
- 何のために提携するのか(提携の目的)、それによって何を目指すのか(目標)を具体的に定義します。 ここが提携の根幹であり、後の条項全ての解釈の基準となります。
- 提携して行う具体的な業務内容、その範囲、そして各当事者が主に担当する役割や責任範囲を明確に定めます。責任の押し付け合いを防ぐためにも重要です。
- 提携の期間(いつからいつまでか)を定めます。プロジェクト完了まで、あるいは一定期間ごとに見直しを行う、などと定めることもあります。
- 提携業務を進める上で発生する費用(開発費、広告費、人件費など)を、どちらが、あるいはどのような割合で負担するのか(費用分担)のルールを定めます。
- 提携によって利益(収益)が上がった場合に、それをどのように分配するか(収益分配)のルールを定めます。計算方法も具体的に記載します。
- 提携にあたって各当事者が持ち寄る情報、ノウハウ、技術などの知的財産権(バックグラウンドIP)の取扱い(相手方にどこまで利用を許諾するかなど)を定めます。
- 提携業務の結果、新たに生み出された発明や著作物などの知的財産権(フォアグラウンドIP)を、どちらに帰属させるか、あるいは共有とするか、その場合の持分割合や利用条件などを明確に定めます。 ここは重要なポイントです。
- 提携を通じて知り得た相手方の秘密情報の取り扱い(秘密保持義務)について定めます。
- (必要に応じて)競業避止義務を定めるか検討します。これは、提携期間中や終了後一定期間、提携内容と競合するような事業を、相手方の許可なく行わない、あるいは他の事業者と協力しない、といった義務です。範囲や期間が広すぎると無効になる可能性もあるため、設定する場合は慎重に検討します。
- どのような場合に提携を解消(契約解除・終了)できるか、終了した場合の措置(開発中の製品の扱い、権利関係の整理、費用の清算など)を定めます。
- 準拠法と合意管轄を定めます。
- 上記を盛り込んだプロンプトを作成し、AIに草案を生成させます。
- 生成された草案を確認し、「提携の目的と範囲」「役割分担」「費用負担と収益分配のルール」「知的財産権(バックグラウンド/フォアグラウンド)の帰属と利用条件」「競業避止義務(設定する場合)」「終了時の処理」が明確かつ公平か、自社の意図に合っているかを確認・修正します。
- 専門家レビューを受け、最終版とします。 提携内容は複雑化しやすいため重要です。
注意すべき点
- 業務提携は協力関係が基本ですが、利害が対立する場面も想定されます。役割分担、費用・収益、知的財産権など、曖昧さを残さず具体的に規定することが、将来の紛争を防ぐ鍵となります。
- 新たに生み出される知的財産の帰属や利用条件は、提携の成果を左右する最も重要な要素の一つです。共有とする場合でも、その後の利用(改良、第三者へのライセンスなど)について細かくルールを決めておくことが望ましいです。
プロンプト例
●[当事者A社](甲)と[当事者B社](乙)の間で締結する業務提携契約書の草案を作成してください。提携目的は『[例:甲の持つ〇〇技術と乙の持つ販売チャネルを活用し、新たな〇〇製品を共同で開発・販売する]』とします。
●提携業務内容と役割分担として、甲は『[例:〇〇製品の基本設計、試作品製造]』、乙は『[例:〇〇製品のマーケティング、販売、顧客サポート]』を担当し、共通の義務として定期的な進捗会議の実施と情報共有を行うものとします。
●提携期間は本契約締結日から『[〇年間/○○○○年○○月○○日まで]』です。
●費用分担は『[例:開発費は甲乙折半/販促費は乙負担/別途協議]』、収益分配は『[例:本提携製品売上から原価等を控除した利益を甲〇%、乙〇%で分配/別途協議]』と定めてください。
●知的財産権については、各当事者が提携前から保有する権利は各々に留保されること、本提携により新たに発生した知的財産権は『[例:甲乙共有(持分割合は別途協議)/貢献度に応じ決定/開発担当者に帰属]』とし、その利用条件は別途協議することを明記してください。
●相互の秘密保持義務に関する条項も必要です。
●競業避止義務として『[例:本契約期間中及び終了後〇年間は、競合製品を相手方の書面承諾なく開発・販売しない/特に定めない]』という条項も(もし必要なら)含めてください。
●重大な違反があった場合の契約解除・終了条件、終了時の清算方法等に関する条項、準拠法(日本法)、合意管轄([○○地方裁判所]、専属的合意管轄)も盛り込んでください。
まとめと最終確認

AIは契約書作成の初期段階(たたき台作成、論点整理など)において非常に有用なツールとなり得ます。しかし、上記で見てきたように、各契約書には特有の法的論点や注意点が多く存在します。
これらの説明をもってしても、AIが生成した契約書案をそのまま利用することのリスク、そして最終的な法律専門家によるレビューの必要性が変わることはありません。 AIを賢く活用しつつも、契約という重要な法的行為においては、専門家の知見を必ず取り入れるようにしてください。